NPO法人群馬県認知症ケア専門士会について

私達、NPO法人NPO法人群馬県認知症ケア専門士会は事務局を県都、前橋市に拠点を置き活動しています。
もともとは厚労省から委託され、都道府県に認知症研修は行っていましたが、委託団体からの補助金増額の要求があり、とても支出できるような額ではなくなったことから、県立高齢者介護総合センター(特別養護老人ホーム・ショートステイ
デイサービス、居宅介護支援所・介護用品展示等を併設)が中心となり、毎日の猛勉強の末、県立施設の研修課や現場(特養)が協力し、これを実施してきました。
その中で、研修修了者から声が上がり認知症介護指導者(認知症介護東京センター研修修了者)や、県で実施してきた認知症介護実践リーダー研修修了者、認知症介護実践者研修修了者を中心とした
有志が集まり、現場での認知症ケアの質の向上を目指し、2006年より認知症ケアを学ぶ任意団体「群馬県認知症ケア研究研修連絡協議会」を立ち上げました。
その後、会計的、法律的な将来性を鑑み2009年には「NPO法人」となり、研修会や講演会、事例検討会、認知症ケア専門士資格取得支援、介護福祉士資格取得支援なども行ってきました。その後、色
々な経過をたどり市民後見人養成事業等の分野の活動にも協力しています。現在の「NPO法人NPO法人群馬県認知症ケア専門士会」は2011年、日本認知症ケア学会の承認を受けて誕生
しています。認知症ケア専門職が認知症の「その人」を理解し、より「その人」に合った望むケアを現場で実践し、常に振り返りのできる、リーダー的役割を発揮できることを主軸において活動しています。
■正式名称・事務所・目的
- 正式名称
- 特定非営利活動法人 NPO法人群馬県認知症ケア専門士会
- 事務所
- 群馬県前橋市天川大島町1441番地
(グループホーム・小規模多機能ホームすずかけの家 内) - 目的
- 認知症ケア専門士又は認知症ケアに関心のある方に対して、認知症ケア研修および認知症ケア研究並びに認知症ケア広報・啓発等に関する事業を行い、もって群馬県内外の認知症ケアの質の向上、および福祉の増進に寄与することを目的とする。
- 社員・会員数
- 理事15名(監事含む)、正会員4名、賛助会員31名、前身会員97名 合計147名登録。2024年度
■活動について
- 理事会
- 毎月1回 対面またはオンライン(ZOOM)
- 総会
- 毎年5~6月(+講演会)
- 事例検討会
- 年間2回。1回につき専門士単位3単位申請。
- 講演会・勉強会
- 年間2回(内1回は総会時)。1回につき専門士単位2単位申請。
- 会員へコラム
- 月1回
- 運営
- 日本認知症ケア学会への単位申請、報告書提出等のやり取り、法務局や県への年間活動、決算の計画、報告等
※認知症ケア専門士の単位を県内で、年間10単位は取得できるような活動を目指す
役員名簿
- 理事長
- 髙橋 将弘
- 副理事長
- 淡路 英子
- 理事
- 福島 富和 名誉会長
- 理事
- 狩野 由子
- 理事
- 深澤 明史 事務局員
- 理事
- 三木 秀明 会計
- 理事
- 高坂 知子
- 理事
- 眞塩 香利
- 理事
- 石川 崇
- 理事
- 山口 怜生
- 理事
- 渋澤 美代子
- 理事
- 眞下 優樹
- 理事
- 黒澤 夕子
- 理事
- 倉林 伸光
- 監事
- 松井 泰俊
- 顧問
- 大沢 幸一
- 顧問
- 小和田 幾野
組織図
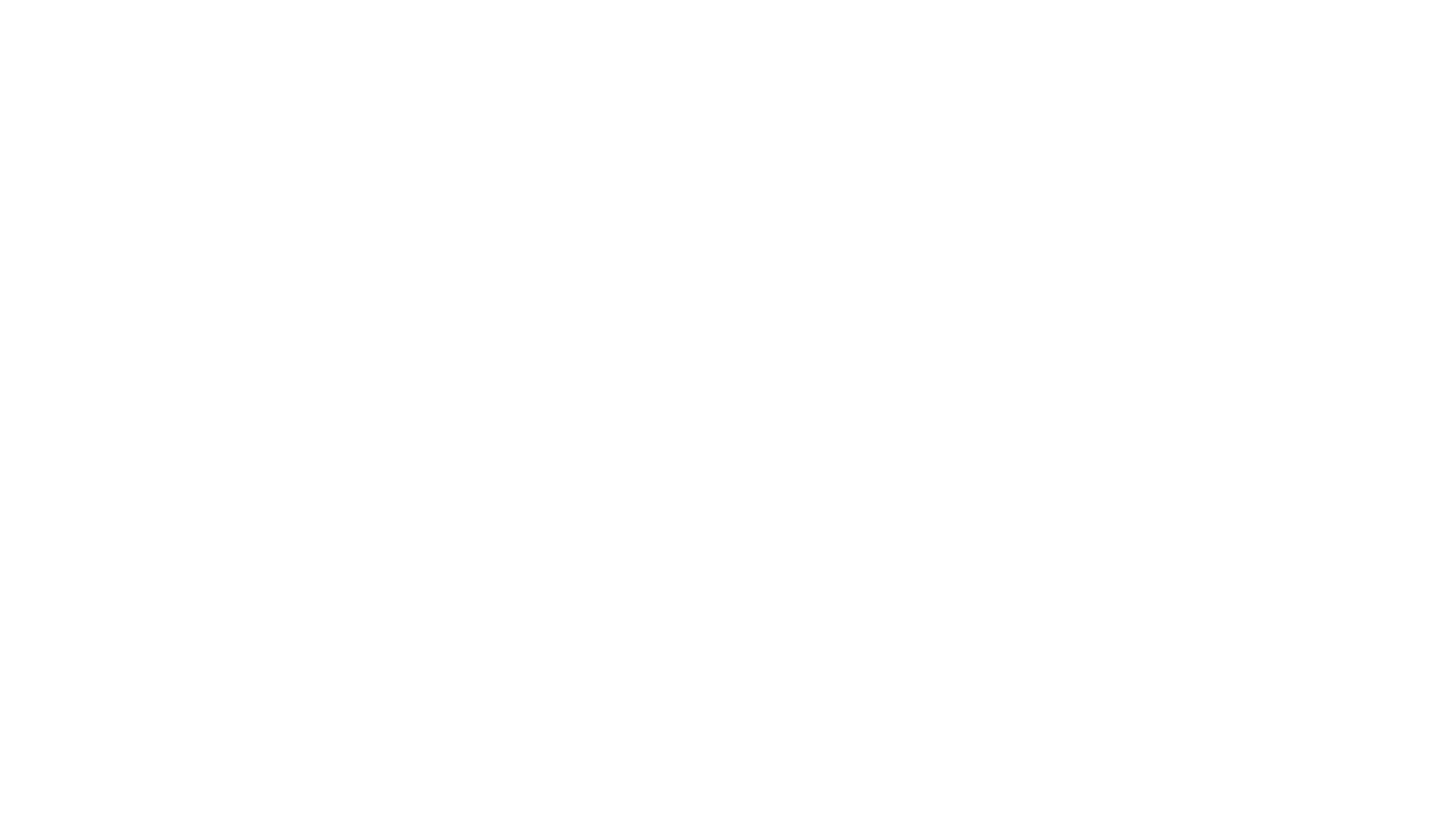
© 2024 NPO法人群馬県認知症ケア専門士会
